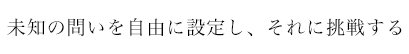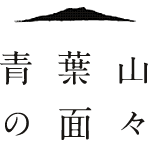光および電子機能を有する有機機能材料の設計に関する研究を行っています。sp2混成炭素原子を主な構成要素とするπ共役系化合物は、非局在化したπ結合性および反結合性軌道を介して、電気伝導、可視~近赤外領域の光吸収や発光、酸化還元等の多様な光・電子機能を発現します。このようなπ共役系化合物の機能は、π共役部位の化学構造のみならず、それらが凝集した固体中での分子の並び方やその向きに大きく依存します。しかし、有機物の凝集構造は一般に予測が難しく、分子設計のみで機能を最適化することは困難です。このため、分子を設計しては、合成し、その固体中での構造と機能を評価し、これらの相関の理解を深めることで、望みの機能を発現させるための合理的な材料設計指針の確立を目指しています。

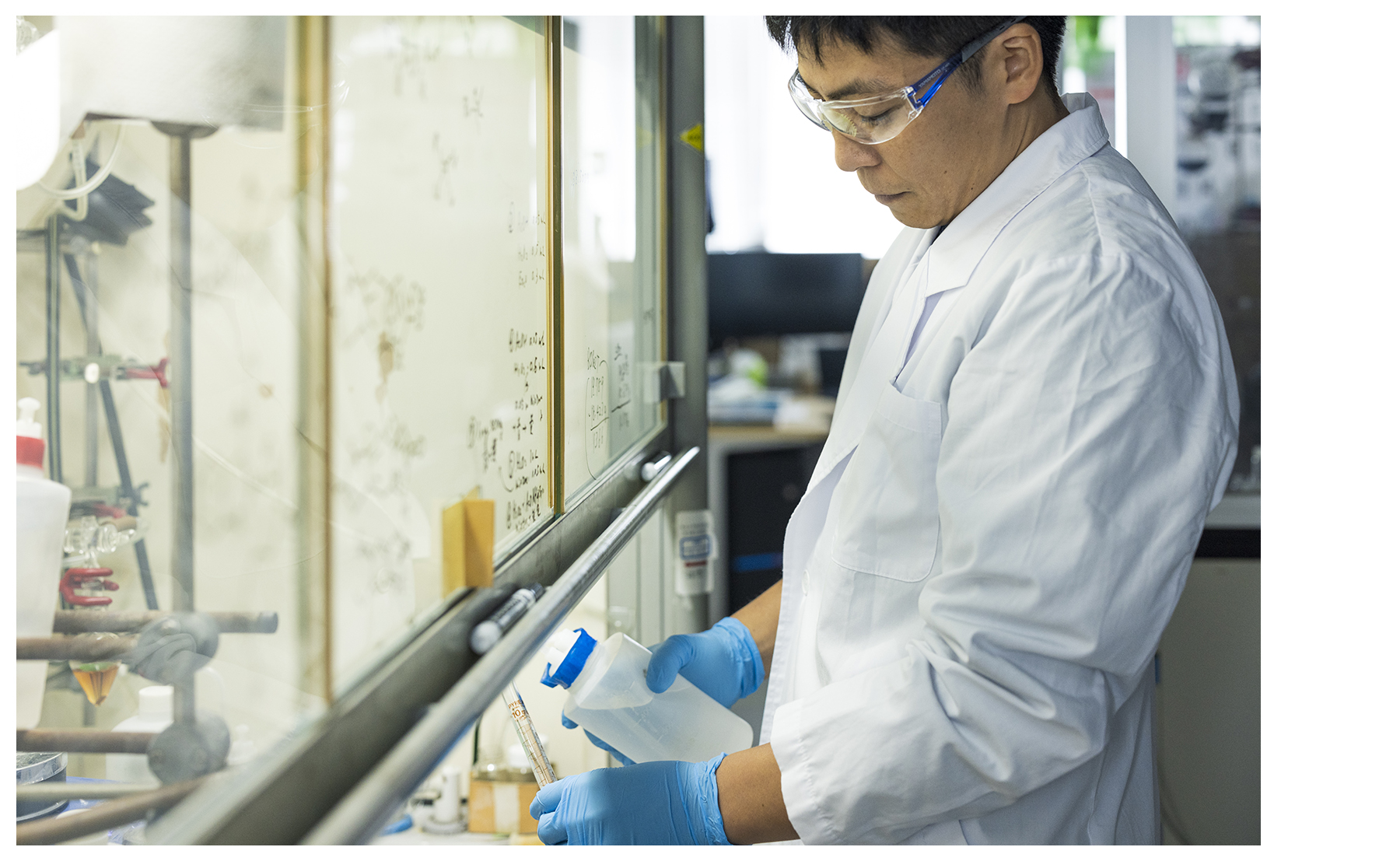
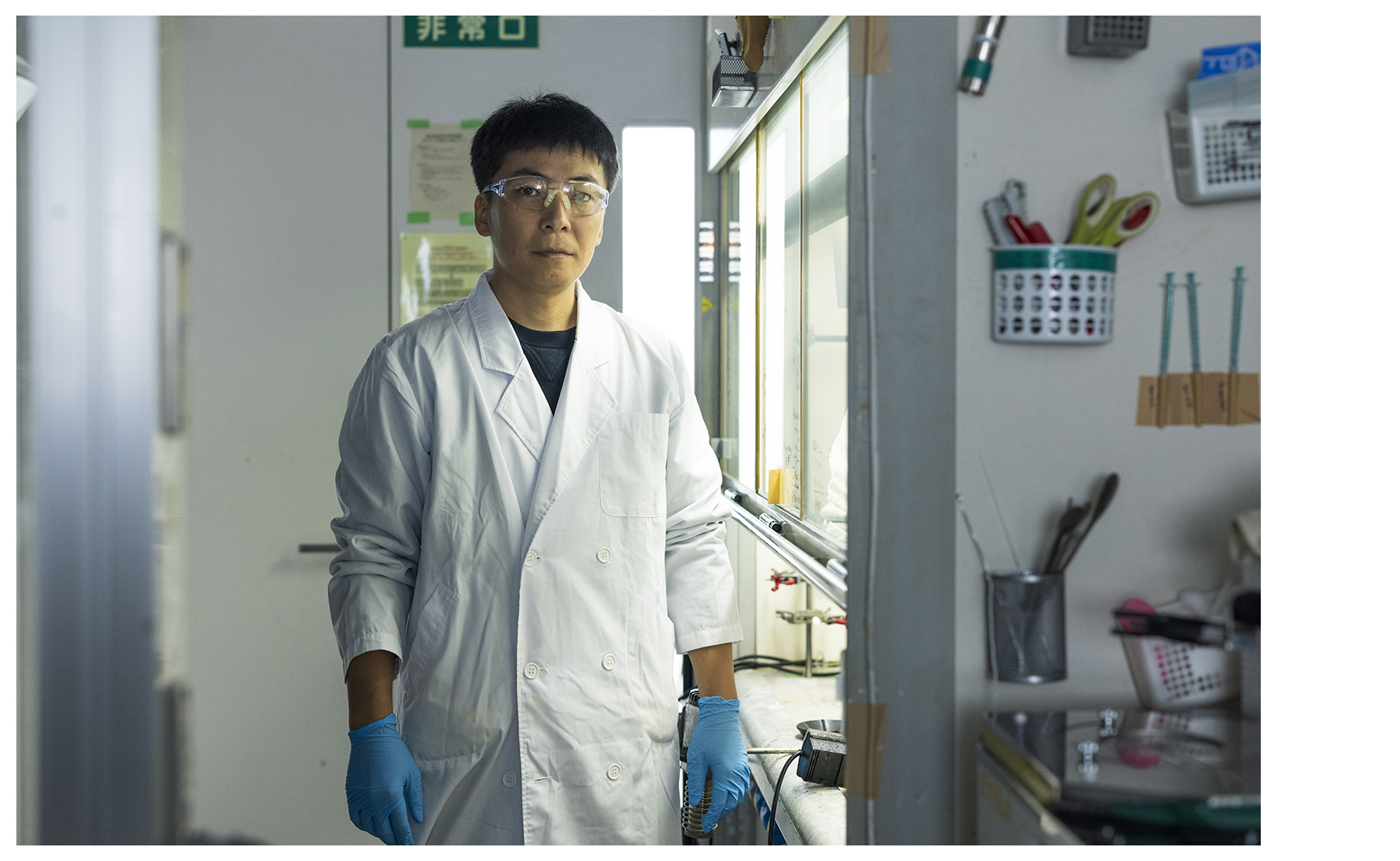
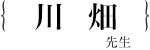
- 名前:
川畑 公輔(かわばた こうすけ) - 所属:
化学専攻 准教授 - 研究室:
有機化学第二研究室 - 出身地:
兵庫県 - 最近読んでいる本:
「宇宙からの帰還」立花隆 著 - 研究分野:
有機機能材料化学 - 掲載日:2025.5.9
1.現在、どんな研究をしていますか?
2.興味を持ったきっかけは?
学生時代に、「鎖状π共役系高分子を向きを揃えて合成する」という研究テーマに取り組んだことが、興味を持ったきっかけです。分子の向きがきれいに揃った高分子膜が示す驚くほど高い異方性(物理的性質が方向によって異なる性質)に魅了され、当時は「向きを揃える」ことに夢中になっていました。現在は、分子の向きだけでなく位置を含めた配列の制御、さらに何をどのように並べるかという分子設計そのものにも重きを置き、真に優れた機能の発現を目指しています。とはいえ、有機分子の凝集構造は極めて複雑で予測困難です。たった一つ原子を入れ替えたり、加えたり、取り除くだけで、分子の配列や機能が予想外に大きく変わってしまうことも少なくありません。こうしたことから、現時点では「制御」と呼ぶにはまだ程遠いのが実情です。一方で、設計した分子の構造や機能について、実際に合成して、実験的に確認してみなければ誰にも分からないことを、自分の目で確かめるのはとてもワクワクします。思い通りの結果にならないことの方が多いですが、これはまだ解明されていないことが多く残されているということの証でもあり、この分野の研究に興味を持ち続けられる大きな理由になっています。
3.メッセージ
研究とは、未解決の問いを自ら設定し、それに対する答えを探求するプロセスです。これは、すでに答えが分かっている事柄を学ぶ、あるいはあらかじめ課題が与えられる学部3年までの座学や実験の授業とは大きく異なります。多くの学生は研究室に配属された後、答えどころか問いすら与えられないことに戸惑うようです。しかし、答えが分かっている問いを理解することと比べて、未知の問いを自由に設定し、それに挑戦することは、はるかに創造的で刺激的な営みです。是非、その面白さを大いに楽しんでもらいたいと思います。