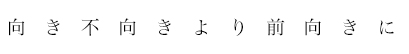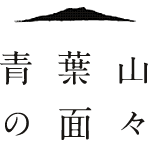「火山防災」の研究をしています。
私は、理学研究科に所属しつつ、社会学的な研究に取り組む文系出身者です。理系の研究科で文系の研究を行っているのは不思議ですよね。
東北大学は、文部科学省「火山研究者育成コンソーシアム構築事業」(2016年度から10年間)の代表機関で、全国18大学の火山研究に取り組む大学院生にフィールド実習や火山学セミナーを提供しています。この事業は2014年御嶽山噴火を契機に企画され、社会科学に基づく防災にも目を配る火山研究者の育成を目指しています。この事業に貢献すべく私は理学研究科に所属し、社会学的な研究に取り組みつつ、次世代の火山研究者の育成に関わっているのです。
社会学の研究手法としては、現地の人に話を伺うヒアリング調査や、広く人の意識を知るアンケート調査など「社会調査」のアプローチをとっています。最近は、箱根火山(大涌谷)を訪れた観光客の方たちを対象に、火山防災意識に関するアンケート調査を行い、自然災害学会で発表しました。よりよい火山防災につながる情報発信のために、どのような伝え方がより効果的かなど、分析・検討しています。
研究と関連して、次世代火山研究者育成プログラムのセミナーを企画したり、パンフレットの作成やWebサイトの記事の作成などの広報、火山学実習の運営、講義なども担当しています。



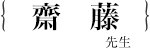
- 名前:
齋藤 さやか(さいとう さやか) - 所属:
理学教育研究支援センター、火山研究人材育成コンソーシアム 准教授 - 出身地:
茨城県 - 最近読んでいる本:
『日本の火山に登る』『天気でよみとく名画』 - 研究分野:
社会心理学、災害情報論 - 掲載日:2024.10.1
1.現在、どんな研究をしていますか?
2.興味を持ったきっかけは?
これまで風水害や地震などの防災に関する研究に取り組んできました。この文科省のプロジェクトをきっかけに、火山防災を学びながら研究し、それぞれの災害の特徴や課題と比較検討することで、新たな視点から防災対策を考え直していけるのではないかと思ったからです。
また、大学生の頃サークル活動で登山を始めたことから「山(火山)」が好きになり、フィールドワーク等で関われるところにも興味を持ちました。
2022年3月に、この事業によるフィールド実習で鹿児島県桜島火山から噴煙が絶えず出ているのを見て「地球は生きている」と、自分と同じように息をしているように感じました。地球上で人が生活していることを考えると、生きた地球とのコミュニケーションこそ防災なのかもしれない、とも捉えられるようになりました。火山研究者は、地球とのコミュニケーションを通し火山のことを知り、私のような文系の社会学などの研究者は、人や社会とのコミュニケーションを通し火山防災の在り方を知ろうとしていると感じました。
複数の分野の研究がつながっていくことで、理学的な知見を社会に還元していけることが増えていくように考えています。
3.メッセージ
私は大学生の頃、お世話になっていた先生から「向き不向きより前向きに」と言っていただいたことが大きな救いになりました。素直に目標に向かえる、合言葉のように感じられたのです。好きでやりたいことと、得意でできることが一致していたら悩むことも少なく良いかもしれません。一方で、興味があり好きでやってみたいけれど、なかなかうまくいかない場合もあると思います。でも悩み過ぎると先に進めなくなってしまいます。そんなとき、思いが強いのであれば、前向きに必要なことを必要なだけ、淡々と取り組んでいくことで、自分の理想に少しずつ近づいていけるものと思います。
「慣れる」ことは、憧れの姿に「なれる」につながっていると感じます。思いを信じて理想に近づいてください。