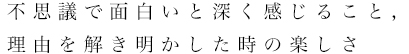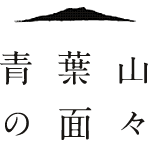金属の周りに原子や分子(配位子と呼ばれる)が結合した物質である“錯体(さくたい)”を合成し,構造や結合を詳しく調べ,それらを触媒として利用する研究を行っています.錯体は,金属と配位子との多様な組み合わせにより,新しい構造や結合を形成でき,それらを活かした機能の発現が可能です.特に,配位子の構成元素や骨格をうまく設計することで,触媒の活性(分子の結合を組み換える力)を向上させるとともに,目的の生成物を与える反応のみを選択的に促進する力を付与できます.
最近は,資源豊富な金属元素(鉄,銅,マンガンなど)を活用して,持続可能性に貢献できる触媒を開発したいと思っております.具体的には,そのような触媒の活性を高めるため,“電気陽性なケイ素をもつ配位子(金属へと電子を押し込む力が強い)を利用すること”や,“複数個以上の金属が集まって反応促進に関与する多核金属錯体(クラスター)を対象とすること”に着目し,研究室の学生さんや先生と共同で実験研究に取り組んでいます.
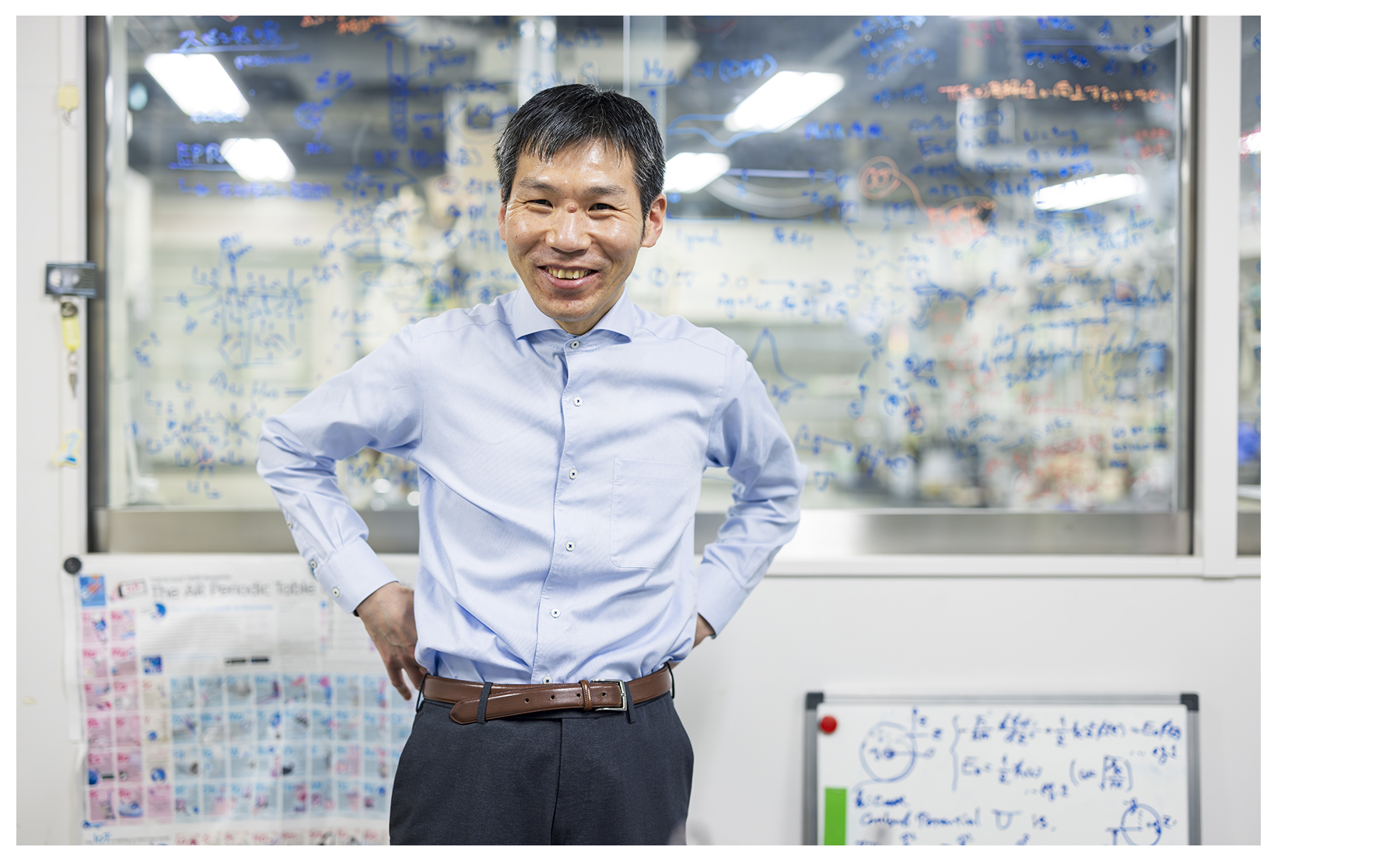
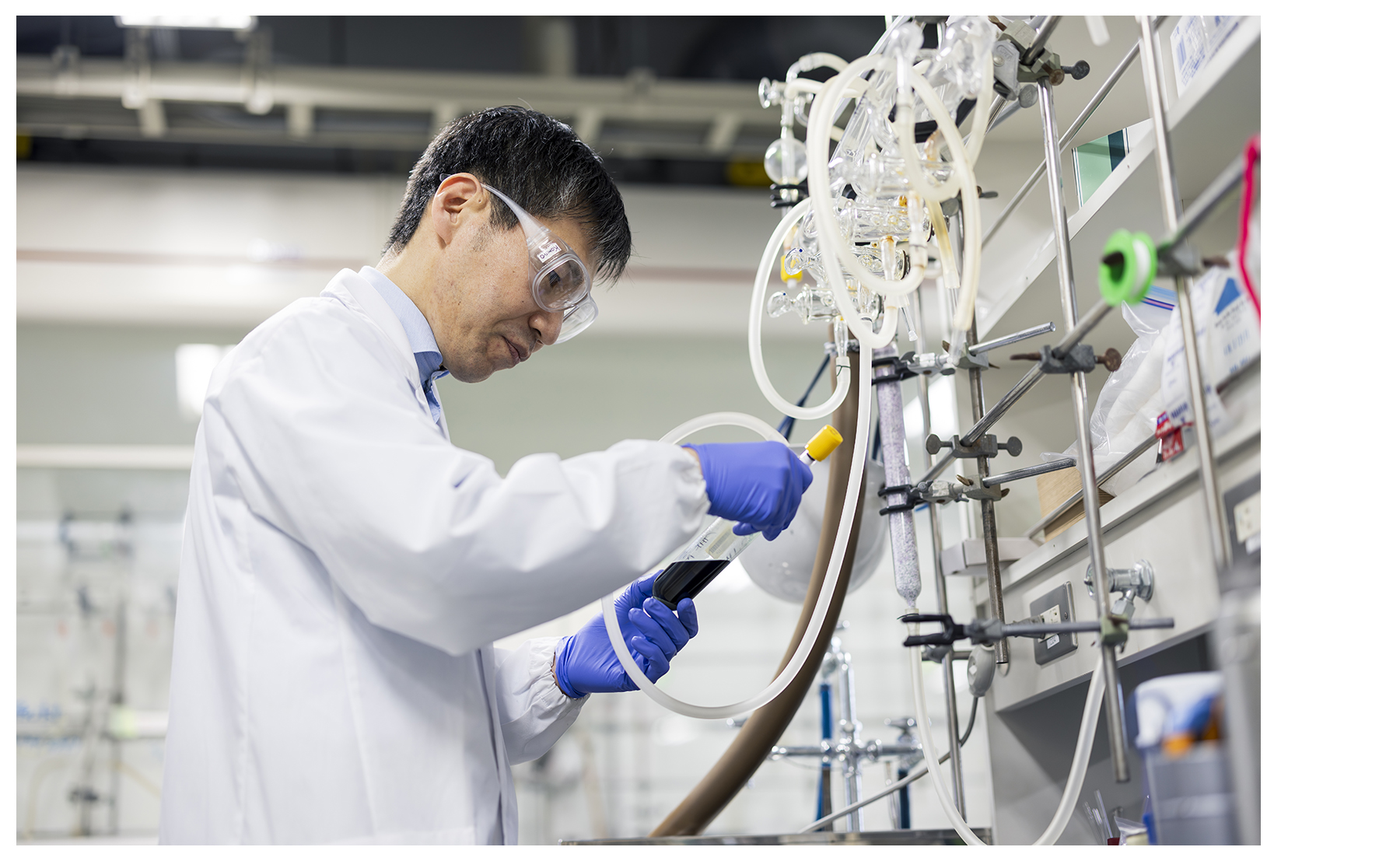

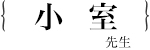
- 名前:
小室 貴士(こむろ たかし) - 所属:
化学専攻 講師 - 研究室:
無機化学研究室 - 出身地:
茨城県 - 最近読んでいる本:
「シュリーマン旅行記 清国・日本」ハインリッヒ・シュリーマン 著(石井和子 訳) - 研究分野:
錯体化学,有機金属化学 - 掲載日:2025.7.2
1.現在、どんな研究をしていますか?
2.興味を持ったきっかけは?
地方育ちのため,生活の中で自然に触れることが多く,理科には小学生のころから強い関心がありました.特に,小中高での理科の先生方からのご指導のおかげで,実験,観察や体験をする機会にも恵まれたことが,理学部への進路を決めるきっかけとなったといえます.化学だけでなく,地学,生物学,天文学などにも興味があり,学科選択の際はどの道に進むか正直悩みました.結局化学を選んだのは,直接目では見えない新しい分子を自分で設計し作ることができることに魅力を感じ,また,化学実験が好きだったことが決め手として大きかったです.最終的には,最初に所属した研究室での先生からのご指導を受けて,金属錯体の形や色の美しさや元素の組み合わせに基づく複雑さに惹かれ,自分もそのような錯体を合成してみたいという思いに至り,現在の専門分野に進みました.
3.メッセージ
大学では,自ら疑問に思い,興味のあることに対して,その解明に向けて探究を行っていく,自由度が高い学びや研究ができます.その分,研究は,「わからないこと」を対象とするため期待通りに進まず右往左往することがしばしばあり,また内容に論理性や専門性が必要となります.ただその根底には,自然や現象に対して不思議で面白いと深く感じることや,理由を解き明かした時の楽しさがあり,個人的にはそれらの感性も大事であると思っております.私自身の研究でも,思い通りの錯体が合成できず,試行錯誤することが多いですが,稀に美しい構造をもつ錯体や,予想外の反応性を示す錯体が得られることがあり,そこが諦めずに研究を続ける活力になっています.理学部の研究に関心のある皆さんには,身近な自然に触れ,実験(学校での授業や大学での公開講座など)を行う体験を通して,自然科学に対する興味関心を深めていくことをお勧めしたいと思います.
青葉山にある東北大学理学部は,最先端の研究設備が揃っており,加えて周りに緑が多く,創造的な研究を行うのに充実した環境です.世界最先端の研究を行っている先生方から直接指導を受けることができ,手厚い教育が行われていることも特色です.ここでの研究を行う道に進んでみてはいかがでしょうか.興味のある方は,オープンキャンパスや模擬講義・交流会(ぶらりがく)に,ぜひ参加してみてください.