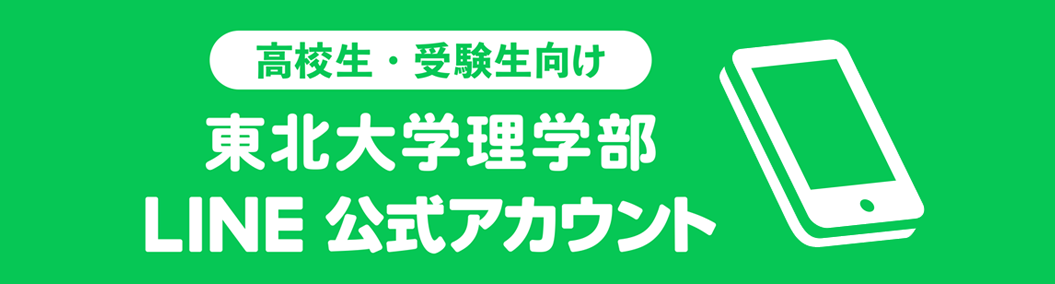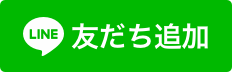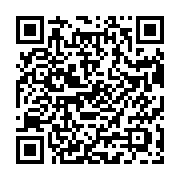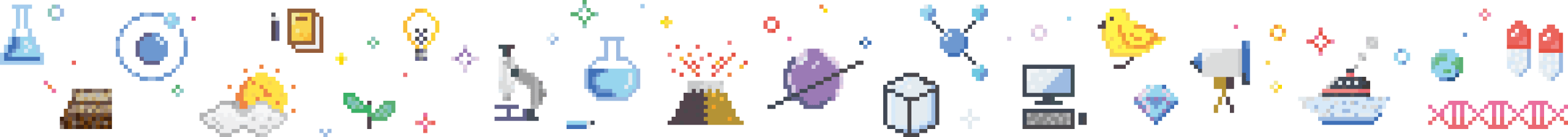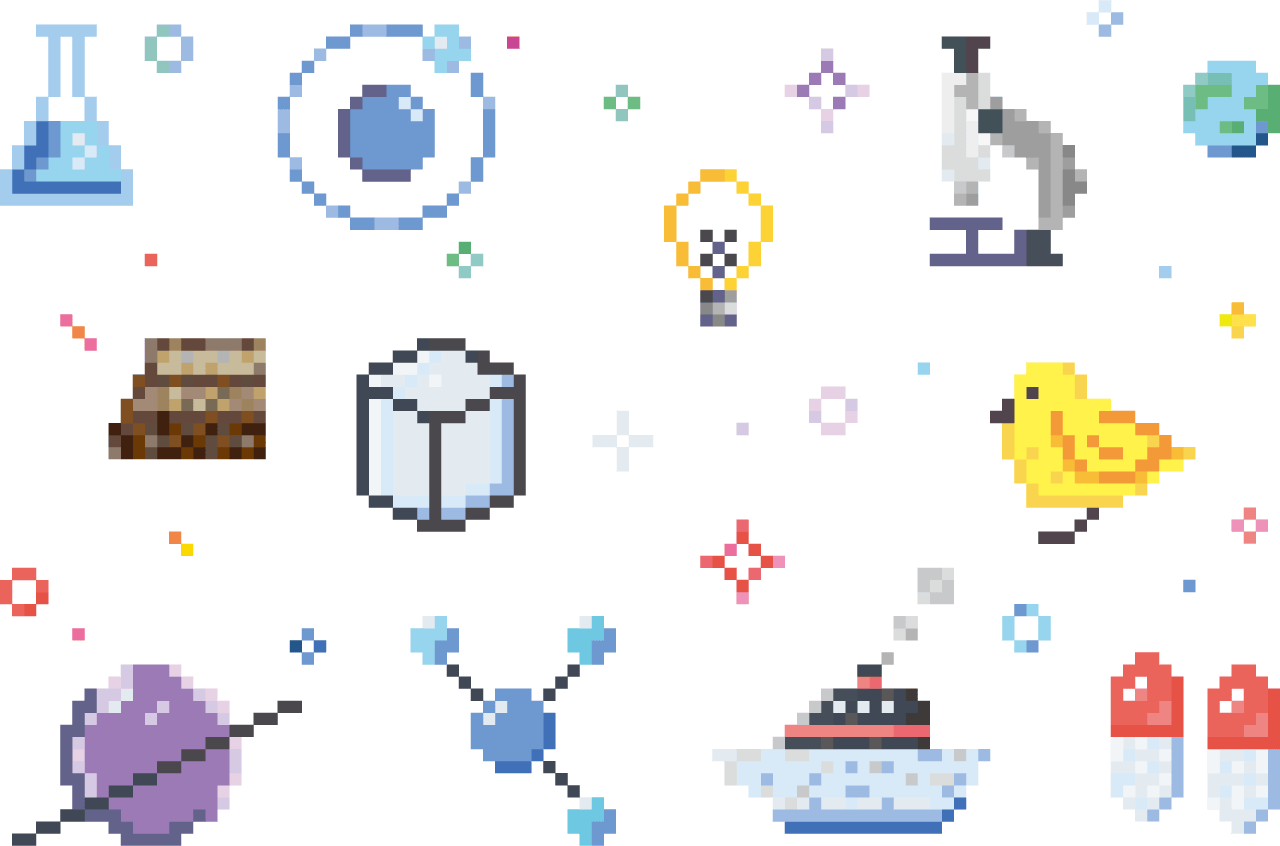理学部入試・進路状況説明会
(午前の部)
9:30-10:10
H-32 大講義棟
H-04 合同C棟 青葉サイエンスホール(中継)
H-16 地学・生物共通講義室(中継)
理学部入試・進路状況説明会
(午後の部)
14:30-15:10
※午後の部は1日目のみ開催
理学部ってどんなところ? AO入試を中心とした入試制度、卒業生の進路・就職先について聞いてみよう!
数学科・物理学科・宇宙地球物理学科(天文学コース・地球物理学コース)・化学科・地球科学系(地圏環境科学科・地球惑星物質科学科)・生物学科の教員・学生が皆さんの質問にお答えします。
受付不要、直接会場にお越しください。
サイエンス・サロン
(理学研究科分野横断研究発表会)
30日 12:00-13:00
多重ゼータ値、巨大ブラックホール、27億年前の海底活動、量子計算機など、理学部の最新の研究について博士課程の大学院生に質問できます。
キャンパスツアー
10:00-(最終グループ終了15:15)
H-11 集合場所:事務棟 1階 総合受付(インフォメーション)後方駐車場
120分で全学科を見学できる毎年人気のキャンパスツアー。先輩がキャンパス内を案内します。
事前予約制/
申込期限:7月7日(月)午前10時/定員:各日135名
下記URLよりお申し込みください。
https://forms.gle/ntS4PDwoAN3iVmig6
※参加者は、受験予定の方に限定させていただきます。保護者の方の参加はご遠慮ください。
※応募者多数の場合は抽選により決定します。
※当日のお申込みはお受けいたしません。
※抽選となった場合を含め、ご参加いただけることになった方にのみ7月10日(木)にメールでご連絡いたします。
理学部の先生たちが講義をします。最前線の研究に触れてみよう!
7/30(水)
|
大講義室 H-32
|
サイエンスホール H-04
|
開場
10:3010:45
~
11:15 |
数学科
一般化等周不等式
~ディドの問題をこえて~
(講師:岡部真也 教授)
|
化学科
固体化学への招待
(講師:福村知昭 教授)
|
開場
11:2011:30
~
12:00 |
物理学科
量子もつれ光子を作る、測る
––– 未来の量子技術に向けて
(講師:金田文寛 教授)
|
生物学科
『動物らしさ』を研究する
(講師:谷本拓 教授)
|
開場
12:4013:00
~
13:30 |
宇宙地球物理学科 天文学コース
金はどこから来たのか?
―マルチメッセンジャー観測で探る重元素の起源ー
(講師:藤林翔 助教)
|
地球科学系 地圏環境科学科
断層を、見る、診る、mill ⁉︎
(講師:武藤潤 教授)
|
開場
13:3513:45
~
14:15 |
数学科
数え上げ ~深まる謎~
(講師:大野泰生 教授)
|
宇宙地球物理学科 地球物理学コース
2024年能登半島地震:これまで分かったこと・これからの課題
(講師:岡田知己 教授)
|
開場
14:2014:30
~
15:00 |
地球科学系 地球惑星物質科学科
顕微鏡の中の太陽系
ー小惑星リュウグウの試料が教えてくれることー
(講師:中嶋大輔 講師)
|
化学科
未来志向の錯体化学
(講師:坂本良太 教授)
|
開場
15:0515:15
~
15:45 |
物理学科
ダークマターの謎
(講師:中山和則 准教授)
|
生物学科
生物多様性
(講師:Jamie M. Kass 准教授)
|
7/31(木)
|
大講義室 H-32
|
サイエンスホール H-04
|
開場
10:3010:45
~
11:15 |
物理学科
ダークマターの謎
(講師:中山和則 准教授)
|
生物学科
生物多様性
(講師:Jamie M. Kass 准教授)
|
開場
11:2011:30
~
12:00 |
数学科
数え上げ ~深まる謎~
(講師:大野泰生 教授)
|
化学科
固体化学への招待
(講師:福村知昭 教授)
|
開場
12:4013:00
~
13:30 |
地球科学系 地球惑星物質科学科
顕微鏡の中の太陽系
ー小惑星リュウグウの試料が教えてくれることー
(講師:中嶋大輔 講師)
|
化学科
未来志向の錯体化学
(講師:坂本良太 教授)
|
開場
13:3513:45
~
14:15 |
物理学科
量子もつれ光子を作る、測る
––– 未来の量子技術に向けて
(講師:金田文寛 教授)
|
生物学科
『動物らしさ』を研究する
(講師:谷本拓 教授)
|
開場
14:2014:30
~
15:00 |
宇宙地球物理学科 天文学コース
金はどこから来たのか?
―マルチメッセンジャー観測で探る重元素の起源ー
(講師:藤林翔 助教)
|
地球科学系 地圏環境科学科
断層を、見る、診る、mill ⁉︎
(講師:武藤潤 教授)
|
開場
15:0515:15
~
15:45 |
数学科
一般化等周不等式
~ディドの問題をこえて~
(講師:岡部真也 教授)
|
宇宙地球物理学科 地球物理学コース
2024年能登半島地震:これまで分かったこと・これからの課題
(講師:岡田知己 教授)
|
9:30−10:10開催の理学部入試・進路状況説明会終了後はスタッフの指示により全員退出していただきます。
10:45からの模擬講義に参加される場合は、一旦退出した後、再度ご入場ください。
DEI推進センター主催
女子中高生のための大学進学やキャリア選択に役立つ講演会&交流会
日時: 7月30日(水)・31日(木) 10:30~16:00
場所:H-04 理学研究科合同C棟多目的室(2階)
*30日と31日は同一のプログラムです(第1部の講演者は日によって異なります)
大学ではどんな勉強や研究をしているの?将来、どんなキャリアが選択できるの?女子が少ない分野でも大丈夫?など、女子中高生のみなさまの疑問に答えるために、東北大学の副学長・理学部OG、女子大学院生(サイエンス・アンバサダー*)・学部生たちが、大学進学やキャリア選択に役立つお話しをします。
*サイエンス・アンバサダーは、次世代の研究者を目指す女子中高校生に「女性研究者ってかっこいい!」という思いを伝える為に結集した東北大学の女子大学院生たち(性自認が女性の方も含む)です。
第1部(13:00〜14:00)
女子中高生のための大学進学とキャリア選択に関する講演会/多目的室
≪副学長による大学における取り組みについての紹介≫
田中真美(東北大学副学長)「東北大学におけるDEI推進:多様な人々が活躍できる大学を目指して」
≪理学部OGによる東北大学での学びとキャリアについての紹介≫
7/30 WED.
- 前田瑞穂((株)日立製作所/2019年度 理学研究科修了)
「極低温物性の解明と,放射線技術のがん治療等への応用 〜大学での経験と企業での研究開発〜」
7/31 THU.
- 小澤友美((株)KPMGアドバイザリーライトハウス/2016年度 理学研究科修了)
「AI時代に社会の道しるべとなる〜課題の本質を見抜いて解決する数学の力〜」
≪サイエンス・アンバサダーによる研究の面白さや魅力についての紹介≫
7/30 WED.
- 日高珠希(サイエンス・アンバサダー/文学研究科)
「環境問題の解決に哲学は必要か?」
- 金井美桜(サイエンス・アンバサダー/情報科学研究科)
「目線に合わせて振動が変わる!映像体験をもっとリアルにする技術」
7/31 THU.
- 前川紗佳子(サイエンス・アンバサダー/農学研究科)
「卵がヒヨコの健康を守る!~ニワトリの卵を介して受け継がれる免疫物質~」
- 瀧口綾音(サイエンス・アンバサダー/教育学研究科)
「学校・教育はどうやって変わるの? 〜持続可能な開発に向けた新しい学びへ〜」
第2部(10:30〜16:00 *第一部の時間帯は休み)
サイエンス・アンバサダーと学部生によるポスタープレゼンテーション/多目的室及び前の通路
サイエンス・アンバサダーと学部生たちが、それぞれ所属している各学部や研究科(文系・理系)を紹介し、進路に関するグループトークでみんなの相談を受けます。気軽に相談し、交流しましょう。
図書館見学
場所:I-02 附属図書館 北青葉山分館
時間: 9:00~16:30(最終入館 16:15)
北青葉山分館は、理学・薬学分野の専門書を中心とした資料を所蔵する図書館です。
個人で集中できる閲覧席のほか、グループで会話をしながら使える個室やオープンスペースも備えています。
大学での学びや研究を支える学習拠点です。
オープンキャンパスでは、図書館の中を自由にご見学いただけます。
また、図書展示も行っておりますので、お気軽にお立ち寄りください。