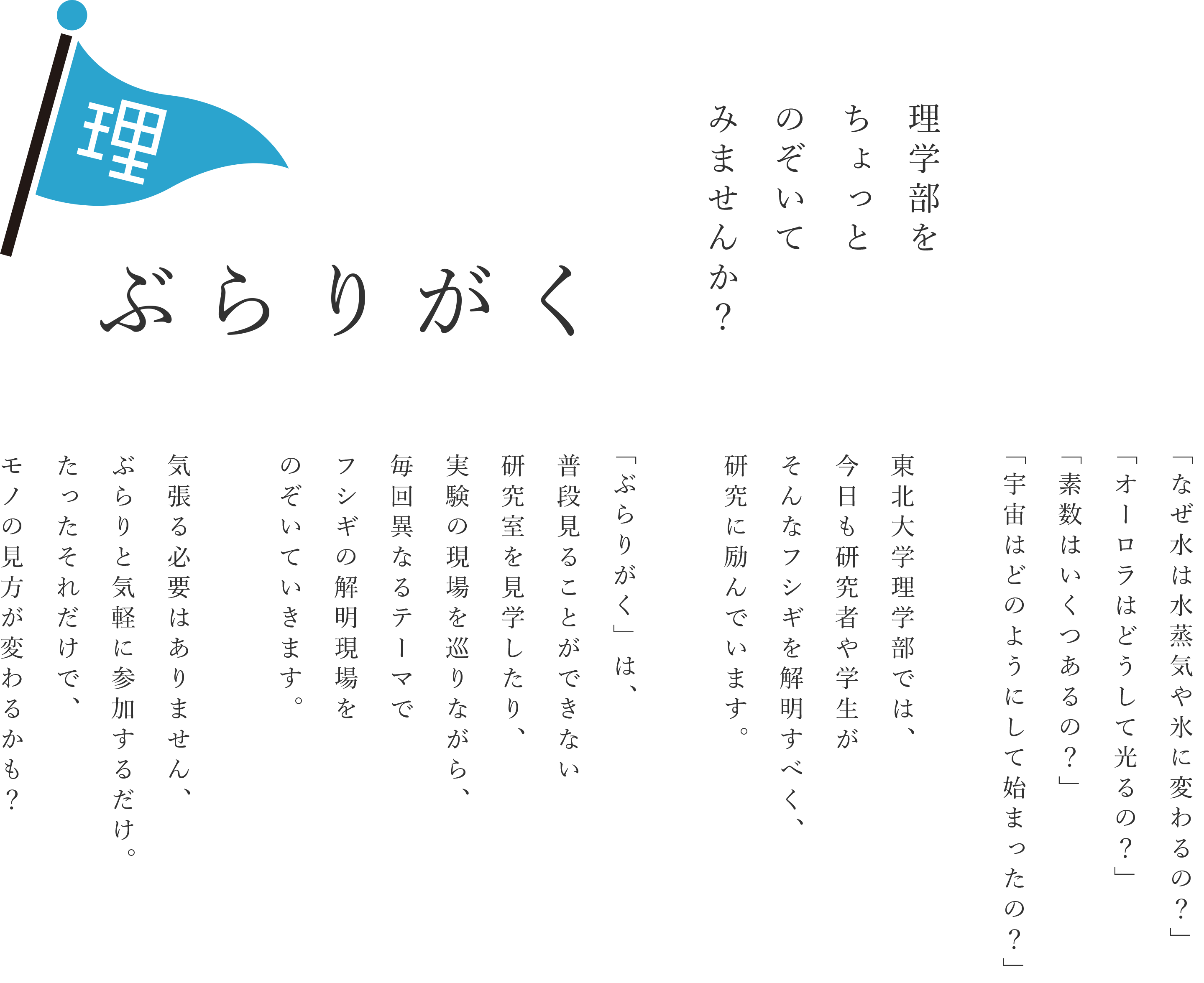次回のぶらりがく
[高校生対象] 2026年3月20日開催
ぶらりがく for ハイスクール with JpGU
本イベントでは、世界最先端の研究を行っている研究者による模擬講義や東北大学理学部・理学研究科の在学生、研究者との交流会を企画しています。みなさんのご参加をお待ちしております!
開催情報*対面開催となります。
 [日時] 2026年3月20日(金・祝)13:00-17:00
[日時] 2026年3月20日(金・祝)13:00-17:00
[会場] 理学研究科合同C棟 2階 青葉サイエンスホール
キャンパスマップ「H-04」の建物です。
地下鉄東西線仙台駅より「八木山動物公園行き」にて9分。青葉山駅にて下車、北1出口から徒歩3分。
[主催] 東北大学理学部・理学研究科/公益社団法人日本地球惑星科学連合
[対象] 高校生(中学生も可)
*講義内容は高校生向けとなりますが、中学生の方もご参加いただけます。
*入場定員が限られますので、会場内の保護者様の同伴はご遠慮ください。
[定員] 先着100名(事前申込制)
[参加費] 無料
[持ちもの] 筆記用具
[お申込み]
ぶらりがく参加規約をよくお読みになり、ご同意いただいた上で
下記URLのGoogleフォームよりお申込ください。
https://forms.gle/a2GPx3NE87VdRdE47
[申込締切] 2026年3月8日(日)
*定員に達した場合は、締切日前でも募集を終了いたします。
<ご登録いただいたメールアドレス宛に、Googleフォームからの回答コピーメールが届きます>
メールアドレスに入力間違いなどがございますと、
回答コピーメールや東北大学理学部からのご案内がお届けできませんので、
お間違えのないようご確認をお願いいたします。
また、「@tohoku.ac.jp」からのメールが受信できるように設定をお願いいたします。
お申込み後、回答コピーメールが届かない場合は、迷惑メールの受信ボックスをご確認のうえ、
東北大学理学部・理学研究科 広報・アウトリーチ支援室までお問合せください。
*定員に達してからのキャンセル待ち受付は行っておりませんので、お早めのお申込みをお勧めいたします。
*状況により、イベント内容が変更・中止となる場合があります。その際は速やかにお知らせいたします。
プログラム
| 12:00-12:30 | ミニ見学 「教室」でも「職員室」でもない、大学生や研究者が普段研究生活を送っている部屋はどのような空間なのでしょうか。リアルな居室をちょこっとお見せします。(所要時間10分程度) *見学希望先着20名限定。ご希望の方は、上記お申込みフォーム[10]の見学ご希望の質問に「はい」をご選択ください。20名に達した時点で[10]の質問は非表示となりますのでご留意ください。 *ミニ見学は定員に達しました。(2026/2/8更新) |
| 12:30-13:00 | 開場・受付(ミニ見学参加者以外の方) |
| 13:00-13:10 | 主催者あいさつ 東北大学理学部長 都築 暢夫 日本地球惑星科学連合 関根 康人(東京工業大学地球生命研究所 所長) |
| 13:10-13:50 | 講義①『三角形の内角の和が180度ではない世界』 東北大学大学院理学研究科数学専攻 助教 阿蘇 愛理  ユークリッドによって紀元前3世紀頃に書かれた『原論』で展開されている平面及び空間幾何学のことをユークリッド幾何学といいます。そこでは、三角形の内角の和が π(180度)になることや、平面上の直線 L と L 上にない点 P を決めたときに P を通り L と平行な直線が1本しか存在しないことが保証されています。しかしこれらの性質は幾何学として本当になくてはならないものなのでしょうか?実はこれらの性質を持たない幾何学を考えても矛盾が生じないことが知られています。この講義では、三角形の内角の和が π より小さい幾何学(双曲幾何学)や π より大きい幾何学(楕円幾何学)などのより一般的な幾何学を紹介し、平面や空間の図形の分類問題についてもお話しします。 |
| 13:50-14:05 | 休 憩 |
| 14:05-14:45 | 講義②『理学でひも解く南太平洋の災害神話』 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 教授 後藤 和久  南太平洋の島々には数多くの神話が残されており、その中には巨大津波や火山噴火、島の消失など災害を想起させるものがあります。実際に過去に起きた災害がモチーフとなっているならば、その痕跡が各地に残されているかもしれません。本講演では、地質学を中心とした学際的研究によって神話に残る各種の災害を立証しようとする取り組みについて紹介します。 |
| 14:45-15:00 | 休 憩 |
| 15:00-15:40 | 講義③『火星衛星探査計画MMXが明らかにする火星圏と太陽系の進化』 東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻 准教授 中川 広務  今年、種子島宇宙センターから火星衛星探査計画Mars Moon eXploration (MMX)が火星圏へ向けて旅立ちます。火星衛星フォボス表面の物質を採取し、地球に持ち帰る「火星圏のサンプルリターン」としては世界初の挑戦です。そこには、火星圏がどのように進化してきたのか、さらに地球の水と生命の起源を知る手がかりがあるかもしれません。本講演では、JAXAを中心に、NASA、ESA、CNES、DLRなど世界の研究機関が連携する国際プロジェクトであるMMXについて、打ち上げ直前の開発状況と目指すべきサイエンスについてご紹介します。 |
| 15:40-15:55 | 休 憩 |
| 15:55-16:55 | 交流会 ー先輩にいろいろ聞いてみようー 小グループに分かれて、理学部・理学研究科の在学生や研究者との交流会を行います。先輩たちがどのような大学生活を送っているのか、東北大学理学部を志望した経緯やどのように入試を乗り越えたのか、パンフレットやWebを見てもわからないことや、今気になっていることを直接聞いてみませんか?今後の進路を考える一助になればうれしいです! |
| 16:55-17:00 | 閉会のごあいさつ |
ぶらりがく参加規約
下記の規約を必ずお読みになり、当規約に同意された上でお申込みください。
また、お申込みされた時点で、当規約に同意されたことになりますことを予めご承知おきください。
- 参加受付後のキャンセルは、キャンセル待ちの方もおりますので出来る限り早めのご連絡をお願いいたします。
無断キャンセルが続いた場合は、以後のぶらりがく参加をお断りさせて頂く場合がございますことをご了承ください。 - 参加申込者以外の見学・参加はご遠慮ください。
- 担当講師及びスタッフの指示に従い、注意事項やマナーを守ってください。
- 実験の際には、器具の取扱い及び怪我には十分ご注意ください。
- 参加者の不注意による事故・怪我等が発生した場合、主催者は責任を負いかねます。
- ぶらりがく開催中のご自身の持ちものに関しては、ご自身で管理願います。
- 見学箇所以外の研究室、実験室等への立ち入りはご遠慮ください。
- 開催内容が事情により変更になる場合があります。
- 本イベントに際し、主催者が参加者を撮影する場合があります。これらの記録物(写真、動画等)は東北大学理学部・理学研究科広報・アウトリーチ支援室の活動報告として、公式ホームページや各種印刷物等に使用・掲載させて頂くことがございますので、予めその旨ご了承ください。当該使用・掲載に問題がある場合は、その旨お申し出願います。
- 参加希望者が未成年の場合は保護者の承諾を得て参加し、主催者側が提示した要保護者同伴の学年に相当する場合は必ず保護者が同伴してください。