2012年8月22日取材
地学専攻 吉田武義教授 最終講義
3月5日(月)、理学部大講義室にて地学専攻の最終講義が行われました。14:00~15:00が吉田武義教授「東北本州弧における島弧火成活動の研究」、15:00~16:00が藤巻宏和教授「 私の研究で会った3人と、ICP-MSによる分析の危うさ」による二部構成で、両先生の最後の講義を受けようと学生、教職員、そして卒業生が大勢参加し、大講義室はほぼ満員になりました。
吉田先生のご専門は火成岩岩石学で、島弧の構成と進化に果たす火成岩の役割について研究、加速器を使った光量子放射化分析、誘導結合プラズマ質量分析法、蛍光X線分析法を駆使してこれらの解明に挑んでおられます。また、最近ではデジタル地質図上にデータベースを構築するといったデジタル地質図の制作にも積極的に取り組まれています。助手時代は昼夜を問わず実験をされていたそうで、その結果、論文・報告書の数は250件を超えています。
その他、第一線で活躍される地学専攻のOBやOGによる講義「現場のフロンティアサイエンス」を新たに開講し、学生たちのキャリア支援にご尽力されました。講義後に開かれるお茶会で、卒業生と学生たちの会話を微笑みながら見守る吉田先生の姿を、もう見ることができないと思うと寂しい気持ちでいっぱいです。
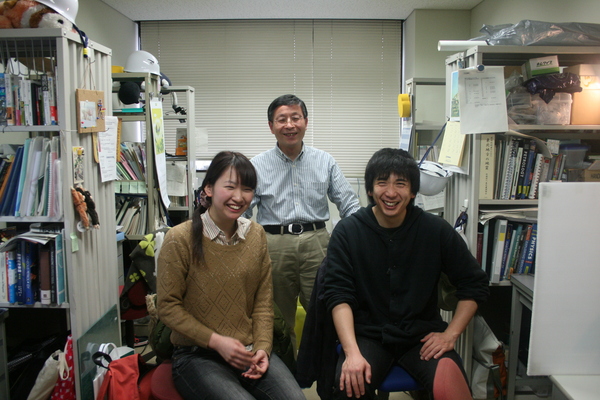
地学の道に進んだきっかけは何ですか?
僕は香川県坂出市の出身なのですが、そこには府中ダムというダムがあります。そのダムは僕が中学生の頃に造られたもので、当時、自宅にはダム建設地質調査のため広島大学出身の若い地質屋さんが下宿していました。その方と次第に仲良くなり、休日になると調査の手伝いをするようになりました。それがきっかけで地学に興味を持ち始めたんだと思います。
高校では地学部に入り、顧問の佐川先生にいろんな所に連れていってもらいました。サヌカイト(讃岐岩)を採取したり、東北大学を勧めてくれたのも佐川先生でした。
学生の頃はどのような研究を?
学部の卒業論文では地元でサヌカイトの研究をしたかったんですが、ちょうど先輩がサヌカイトで博士論文を書いていて、同じテーマは避けようと思い石鎚山に変更しました。石鎚山へ卒論調査で入るときは、香川県の実家を車で出発し、まずは地図をもらいに高知の営林局へ、その後目的地である愛媛の石鎚山へ...というルートでした。長距離運転を心配した父が助手席に同乗していましたが、目的地に着く手前の山中で、私が居眠り運転をして車ごと崖から谷へ落ちてしまいました。幸い車が一回転した後、崖の途中で木にひっかかって、僕は無傷で済みましたが、助手席で寝ていた父は少し怪我をしてしまいました。父に後の処理は俺がやるからと言われ、事故現場からリュック一つで歩きはじめたのが、私の調査のスタートでした。その後、実家に戻った父は母や祖母に相当怒られたそうです。
学生のみなさんへメッセージをお願いします
僕のモットーでもあるこの言葉をメッセージとさせていただきます。
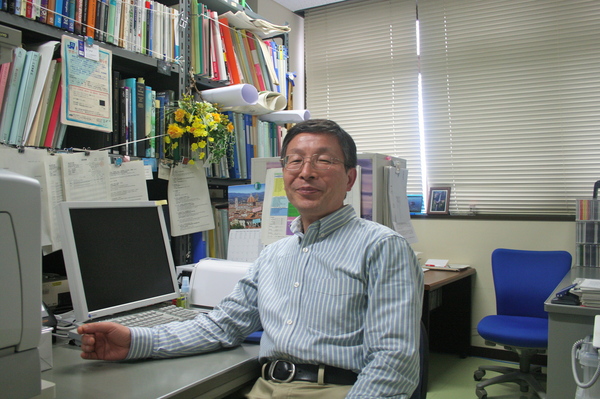
吉田先生のご専門は火成岩岩石学で、島弧の構成と進化に果たす火成岩の役割について研究、加速器を使った光量子放射化分析、誘導結合プラズマ質量分析法、蛍光X線分析法を駆使してこれらの解明に挑んでおられます。また、最近ではデジタル地質図上にデータベースを構築するといったデジタル地質図の制作にも積極的に取り組まれています。助手時代は昼夜を問わず実験をされていたそうで、その結果、論文・報告書の数は250件を超えています。
その他、第一線で活躍される地学専攻のOBやOGによる講義「現場のフロンティアサイエンス」を新たに開講し、学生たちのキャリア支援にご尽力されました。講義後に開かれるお茶会で、卒業生と学生たちの会話を微笑みながら見守る吉田先生の姿を、もう見ることができないと思うと寂しい気持ちでいっぱいです。
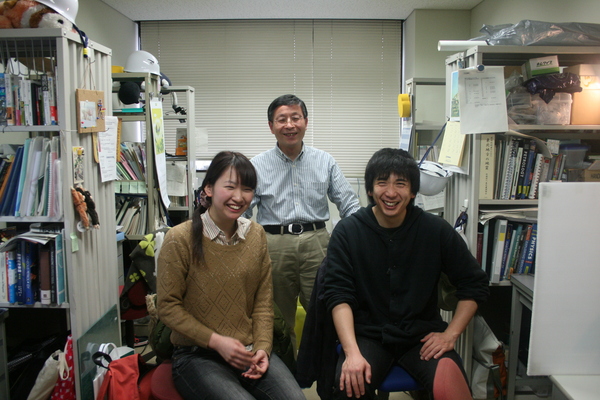
▲研究室で:吉田先生と学生たち
■□■吉田先生に地学との出会いについてお話をお伺いしました■□■
地学の道に進んだきっかけは何ですか?
僕は香川県坂出市の出身なのですが、そこには府中ダムというダムがあります。そのダムは僕が中学生の頃に造られたもので、当時、自宅にはダム建設地質調査のため広島大学出身の若い地質屋さんが下宿していました。その方と次第に仲良くなり、休日になると調査の手伝いをするようになりました。それがきっかけで地学に興味を持ち始めたんだと思います。
高校では地学部に入り、顧問の佐川先生にいろんな所に連れていってもらいました。サヌカイト(讃岐岩)を採取したり、東北大学を勧めてくれたのも佐川先生でした。
学生の頃はどのような研究を?
学部の卒業論文では地元でサヌカイトの研究をしたかったんですが、ちょうど先輩がサヌカイトで博士論文を書いていて、同じテーマは避けようと思い石鎚山に変更しました。石鎚山へ卒論調査で入るときは、香川県の実家を車で出発し、まずは地図をもらいに高知の営林局へ、その後目的地である愛媛の石鎚山へ...というルートでした。長距離運転を心配した父が助手席に同乗していましたが、目的地に着く手前の山中で、私が居眠り運転をして車ごと崖から谷へ落ちてしまいました。幸い車が一回転した後、崖の途中で木にひっかかって、僕は無傷で済みましたが、助手席で寝ていた父は少し怪我をしてしまいました。父に後の処理は俺がやるからと言われ、事故現場からリュック一つで歩きはじめたのが、私の調査のスタートでした。その後、実家に戻った父は母や祖母に相当怒られたそうです。
学生のみなさんへメッセージをお願いします
僕のモットーでもあるこの言葉をメッセージとさせていただきます。
「汗をかき 恥をかき ものを書く」
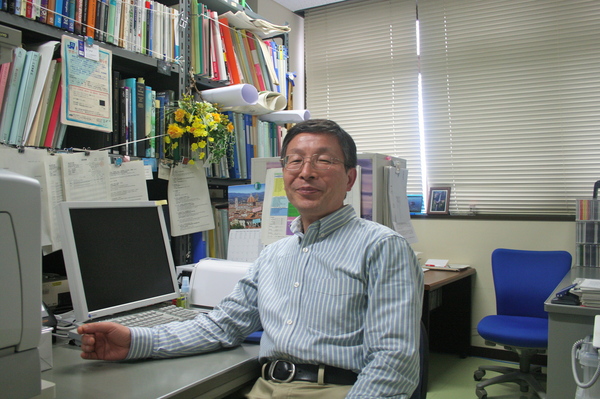
▲退官後も宿題がいっぱいあると語る吉田先生
*Photo Gallery*









