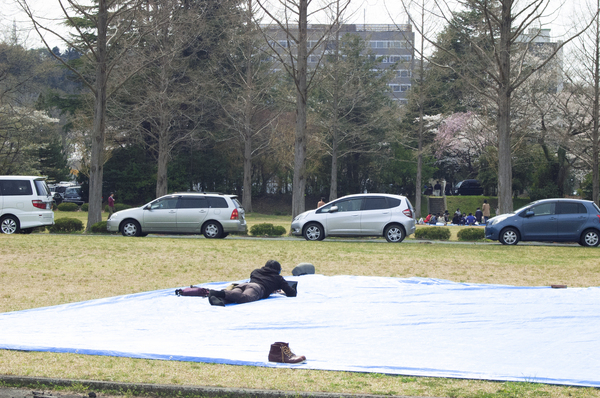自修会コンサートが開催されました
10月27日(月)、理学部・理学研究科自修会主催のコンサートが開催されました。自修会では年に数回、プロの方をお招きしてコンサートを開催しています。プロの方と学生の共演は、その成長ぶりを確認できるのもあって毎回楽しみです。今回は宮城教育大学音楽科の学生も加わって、更に音に厚みがでたのではないでしょうか。
このような楽しい企画を運営してくれているスタッフの学生さん、いつもありがとうございます。
↑写真をクリックするとスライドショーになります
平成26年9月修了・卒業者の学位記交付式が行われました
9月24日、北青葉山厚生会館2階レストランAOSISにて、平成26年9月修了・卒業者の学位記交付式が行われました。参加者は46名(本人以外含む)でした。3月の学位記交付式と違い留学生が大半を占め、国際色豊かな式となりました。
修了生、卒業生みなさま、修了・卒業おめでとうございます。 さらなるご活躍を心から祈念いたします。
☆ 写真をクリックするとスライドショーになります
理学部自修会主催のコンサートが開催されました

今回は、パリ・オペラ座のピアニストであるベッセラ・ベロフスカさん、日本フィルハーモニー交響楽団の第一バイオリン奏者である松本克巳さんをお招きしてのデュオ演奏、さらには東北大学交響楽団有志との共演が実現しました。このコンサートは理学部自修会のメンバー、東北大学交響楽団のみなさんなど、多くの学生たちが実行委員として活躍、事前の準備や広報活動(OH!バンデスで生放送告知もしました!)、当日も受付などで忙しく働いている姿を多く見かけました。
ホールの入口にたくさんのお客さんが並んでくださったため少し早めに入場を開始、約250名の方にご来場いただきました。
第1部はベッセラさんのピアノと松本さんのバイオリンによるデュオ演奏、ヴィヴァルディの『四季』を解説を交えながら演奏してくださったり、松本さんが『ユーモレスク』を演奏しながら客席に降りてくださるという、うれしいハプニングもありました。第2部ではベッセラさんをソリストに、松本さんを第1バイオリンにお迎えして東北大学交響楽団有志との共演でモーツァルトの『ピアノ協奏曲 第19番』が演奏されました。最後のアンコールでは、ベッセラさんがピアノソロで6曲を演奏、観客のみなさんから惜しみない拍手が贈られました。
また、会場では理学部の紹介パンフレット「理学部物語」などを配布しました。このコンサートをきっかけに、より多くの方に理学部の活動を知って頂けたのではないでしょうか。
【プログラム】
第1部
エルガー 愛の挨拶
マスネ タイスの瞑想曲
ドヴォルザーク ユーモレスク
ヴィヴァルディ 『四季』より
第2部
モーツァルト ピアノ協奏曲 第19番
☆アンコール(ベッセラさんのソロ)☆
ショパン 24の前奏曲集 第4番 ホ短調 Op.28-4
モーツァルト ピアノソナタ K.331 3楽章「トルコ行進曲」
ショパン 練習曲ハ短調 Op.10-12 「革命」
ハチャトゥリアン 剣の舞
ショパン 24の前奏曲集 第16番 変ロ短調 Op.28-16
ベートーヴェン ピアノソナタ 第14番 嬰ハ短調 1楽章「月光」

☆ 写真をクリックするとスライドショーになります
女川向学館の出前授業レポート
2014年8月22日(金)に、天文学専攻の野間千菜美さん(M2)と岩崎仁美さん(M1)が女川向学館で出前授業を行いました。そのお二人の出前授業のレポートです
女川町は宮城県中部にあり、山と海に囲まれた自然豊かな町です。
太平洋に面しており、有名な女川漁港で美味しい海鮮丼やカキなど海の幸を味わうことができます。わたしたちが女川町に訪れた際もとても美味しい海鮮丼をいただきました。
しかし、2011年3月11日、東日本大震災の際に津波に襲われ沿岸部は壊滅的被害を負いました。今回わたしたちが訪れた「女川向学館」は、主に小・中学生に学習指導と心のケアを行う 被災地の放課後学校「コラボ・スクール」の1校目です。仮設住宅や避難所などで暮らし、落ち着いて勉強する場所を失った子どもたちのために設立されました。
わたしたちがはじめて向学館に出前授業をさせていただいたのは昨年2013年の夏からです。昨年は助教の授業の手伝いをし、神話や宇宙について少し紹介しました。夜の観望会も企画していましたが、あいにくの天気で星空を紹介することができませんでした。女川町は星がきれいに見えると伺ったので、ぜひ実際に空をみて、宇宙や星について知ってほしいと思いました。そこで今年ももっと星について知ってもらおうと出前授業を企画しました。
たいていの子どもは勉強が嫌いです。わたしが小学生の時も勉強が好きと言っている友達はほとんどいませんでした。
今の日本ではどうしても「これはテストに出るから覚えなさい」という詰め込み型の授業になりがちです。理科が嫌いな子どもの多くは「難しい」とか「暗記が嫌」とか「そもそも興味がないし勉強する意味が分からない」と考えているのではないでしょうか。
勉強に必要なのは「知りたい」と思う気持ちで、難しい暗記や数式は必要ありません。私たちは「?」が「!」になる喜びを知ってもらい苦手意識をなくしたい、純粋に学ぶことを楽しんでもらいたいと考え出前授業を企画しました。
今回の授業では「星は天球に張り付いているのではなく、ひとつひとつ地球からの距離が違う」ということ、「天の川は銀河を内側から見たものである」ということ、つまり「宇宙の立体構造」の理解を目標にしました。小学校低学年には少し難しいテーマですが、自作の教材やmitaka(http://4d2u.nao.ac.jp/html/program/mitaka/)を用い、星や天の川がどのように分布しているのかを実際に目で見て感覚的に理解してもらえるような工夫をしました。
また、実際に星空を見てもらうことで宇宙を身近に感じ、より興味を持って欲しいと考え、星座早見盤をひとりひとり作成してもらい観望会を行いました。女川町は星空がきれいだと伺っていたので、星座早見盤の作成を通して今回の授業後も自主的に星を見上げてもらいたい、というねらいもあります。
今回の出前授業は小学生から中学1年生を対象としました。幅広い学年が一緒になって授業をうけるため最初は緊張しているようでしたが、徐々に打ち解けていったようです。小学1、2年生には少し難しい内容を中学生が教えてあげる場面も見られ、違う学年で一緒に授業をうけることがよい刺激になったのではないかと思います。
また授業中の様子についてですが、星や惑星についてよく知っている子が多かったです。ほかにも星座に興味をもっている子が多く、話を熱心に聞いてくれました。今まで生徒たちが断片的に知識として知っていたことを授業の中でつなぎ合わせることで星についてより深い理解につながったのではないかと思います。また、工作の時間に星座早見盤を作りましたが、とても一生懸命作っている姿が印象的でした。星座早見盤が完成すると、「どうやって使うの~?はやく使ってみたい!!」など外に出て使うのが待ちきれない様子でした。懐中電灯に赤色のセロファンをはり、いざ外にでてみると雲の隙間から夏の大三角形が見えていました。普段あまり星を見ないといっていた生徒たちですが、実際に自分たちの目で星を見て、これからも見てみようと言っていたのがとてもうれしかったです。今回の授業で作った星座早見盤は一年中使うことができます。さらに見た星をチェックできるようシールも一緒に渡したので、作った星座早見盤で星空を見上げる機会が増えればいいなと願っています。(岩崎さん)
当初の予定では小学校高学年を対象としていましたが、募集をかけてみると小1から中1まで幅広い学年が集まりました。当然知識や考えていることも学年によって違います。参加者同士はほぼ初対面だった様で最初はとても静かで戸惑っている様子だったのですが、アイスブレイクとして行った天文二択クイズでの岩崎さんの見事な進行により、徐々に空気が和らいでいったように感じました。
もともと星や宇宙に興味がある子どもたちが集まったということもあり、私たちの話もとても熱心に聞いてくれていました。一方的に話をする場合、途中で飽きてしまったり聞いてるようで聞いていないことが多いのですが、飽きることもなく理解しようという姿勢が見られました。途中でわからなくなってしまった小学生に、それまでおとなしかった中学生が自ら積極的に教えてあげている姿が非常に印象的でした。私たちとしては、なんとなく自分の中で授業の内容を理解して興味をもってくれればいいなというくらいにしか考えておらず、参加者同士のそういった交流は期待していなかったので、良い意味で期待を裏切られました。
お話のあとにひとりひとり星座早見盤を作成してもらいましたが、みんな夢中になって作っていました。進度や出来栄えは人それぞれですが、やはり自分で作ると愛着がわくようで、使い方を教えると教室の中なのにうれしそうに上を向いてくるくる回していました。見ることができた星を記録できるようにと星の形をしたシールを配りました。観望会は時間と天気の都合で少ししか星を見ることができませんでしたが、私たちが教えた星以外に自分で星座早見盤を使って星を探し、見つけた星にシールを貼っている子どももいました。普段は星を見ないと言っていましたが、これをきっかけに星空に目を向けてくれるのではないでしょうか。(野間さん)
今回はじめてわたしたちが主体となり授業を行いました。小学生から中学1年生と学年が幅広く混ざっているので内容をわかりやすく伝えるのがとても難しかったです。中学生にとってはもう知っていることかもしれませんが、みんながわかるように丁寧に説明することを心がけました。授業を実際にやってみて一番驚いたことは、生徒たちが宇宙や星についてよく知っているということです。わたしたちに一番身近な太陽と月をはじめとして、太陽系の惑星の特徴や星座の形などを知識として知っていました。興味を持ったことに対して自分たちで調べたりしていたのでしょうか、○×問題の際も正答率が高いのでひやひやしました。今回の授業のメインの話は「宇宙を立体的に考えてみよう」ということです。星座をつくる星については知っているけど、どんな風に宇宙に星があるのか、また、星が集まって天の川となりますが、なぜわたしたちには川のように見えるかなど、知ってはいるが想像が難しいことを紹介しました。生徒たちがすでに知っている知識をより深めることができたと思います。これを機に知識を得るだけではなく、実際はどうなっているのかなど自分たちで考える機会が増えればと思います。また、これだけ宇宙や星について興味がありながら、実際に星を見ることはあまりないというのにも驚きました。やはりなかなか夜に星を見に行くという機会がないのでしょうか。今回の授業を通して学んだ宇宙の立体構造について、実際の星空を見上げながら、空いっぱいにひろがる星と天の川について考えてもらえることを期待しています。(岩崎さん)
先にも述べましたが小1から中1まで幅広い学年が参加したため、授業の内容や組み立て方については非常に悩みました。私たちが主体で授業をするのは今回が初めてであるにも拘わらず、その上中学生でも飽きない、小1でもわかる授業を作るというのは正直不可能なのではないかと感じていました。
テーマとしては「宇宙の立体構造」を選び、小学生にもわかりやすいような工夫をこらしたつもりでしたが、案の定最初は「?」という顔をしていました。どこまでわかってどこがわからないのかを聞き、少し時間をかけて何度も丁寧に説明するとなんとなくわかってもらえたようでしたが、改めて「伝えることの難しさ」を感じました。それと同時に「会話をすることの大切さ」も感じました。一方的に話すのではなく、ひとりひとりの反応を見て必要に応じて会話をし、説明を加えることで誰ひとり置いてきぼりにすることなく授業を終えることができたのではないかと思います。
小中学生はパワフルで好奇心旺盛でした。私たちが「そういうものなのだ」ですませてしまうことでも「なんで?どうして?」と疑問に思うことが多いのでしょう。今回の授業で科学者にもっとも重要な「何事も疑問に思う心」を子どもたちに教えてもらいました。
これからも知的好奇心を大切に、そしてこの授業で身の回りの自然現象の不思議を考える楽しさに気づいてもらえれば幸いです。(野間さん)
☆ 写真をクリックするとスライドショーになります
『化学グランプリ2014』二次選考を東北大学で開催
8月22日(金)~23日(土)、一次選考を通過した74名の中高校生が川内北キャンパスの学生実験棟に集結して、『化学グランプリ2014』の二次選考に挑戦しました。これまで関東と関西地区で開催されてきた化学グランプリの実技試験。昨年度、被災地の高校生にも化学の夢を届けたいとの願いを込めて、初めて東北地区(東北大学)で開催。見事に東北地区の受験生が大賞を受賞しました。今年も東北地区の受験生に期待が集まりました。果たして東北勢の結果は...
宮城県仙台第二高等学校の石垣貴史さんと福島高校の小山田健太さんが金賞を受賞しました。おめでとうございました。今年度で二次選考の東北大学開催は終わりましたが、2回とも東北地区から入賞者が出るという明るいニュースをお届けできて良かったです。
二次選考は「金属錯体の合成と構造」という大学生レベルの実験・考察でした。
東北大学大学院理学研究科 合同入試説明会2014が開催されました
5月10日(土)、東北大学東京分室(サピアタワー10階)にて東北大学大学院理学研究科合同入試説明会が開催されました。 2009年から6回目を迎え、当初に比べ参加者も増えてきて毎年の恒例行事となった感があります。今年は自己推薦入試が早まったこともあり、地球物理学専攻は仙台での説明会・研究室見学会が終わってからの開催ということになりました。
実行委員長の美齊津先生による全体のスケジュール説明、教務委員長の日笠先生による理学研究科の紹介の後、各専攻にわかれて入試、各研究室の紹介を聞く形になっています。特に学生によるキャンパスライフの紹介や分野別に個別相談できるところが合同入試説明会の特徴になっています。
参加者75名
【内訳】 数学 22名(前年度9名), 物理学 33名(前年度23名), 天文学 4名(前年度15名), 地球物理学 5名(前年度13名),
化学 8名(前年度8名), 地学 3名(前年度8名)

↑写真をクリックするとスライドショーになります
【物理系】新入生研究室見学会が開催されました
新入生は入学してしばらくの間、全学教育科目を行う川内キャンパスがメインとなり、物理系研究室がある青葉山キャンパスに来ることはそれほど多くありません。そのため、物理系では新入生が入学手続きで青葉山に来る機会を活用して研究室見学会を行っています。今回、先生や先輩たちと直接お話をしたり、最先端の実験装置を見学することで、物理系に進学した実感が湧いてきたのではないでしょうか?
また、この日見学できなかった研究室でも気になっているところがあれば、自分で先生方に連絡をとって見学の相談をしてみましょう。自分のやりたいことや学科、配属される研究室を考える時の良い参考になると思います。

物理学科ホームページ
宇宙地球物理学科地球物理学コースホームページ
宇宙地球物理学科天文学コースホームページ
新入生オリエンテーションが実施されました
このオリエンテーションでは、カリキュラムの履修方法やサークル活動など、大学におけるあらゆる活動のアドバイスなどが行われ、新入生にそれを参考にして充実した学生生活を送ってもらうことを目的としています。
入学式翌日に1泊2日ということもあって緊張した新入生も多かったと思いますが、このオリエンテーションでまわりのみんなと仲良くなれたという話を先輩方からよく聞きます。みなさんにとっても実りあるものになったのではないでしょうか?

川内萩ホール前にて
2014年4月16日写真日記桜満開
春ですね。理学研究科がある青葉山でも桜が満開になりました。みなさんの研究室ではもうお花見やりました?
 北青葉山憩い公園
北青葉山憩い公園【おまけ】
今は「ナルコユリ」の旬だそうです。食べるとアスパラガスのような味とのこと。薬用植物園の大場さんに少しお裾分けしていただきました。塩少々のお湯でさっとゆがいてマヨネーズで食べるらしい。

広報・アウトリーチ支援室
〒980-8578
仙台市青葉区荒巻字青葉6-3
理学研究科物理系研究棟 725号室
月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30
TEL:022-795-6708
mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp
※[at]を@に置き換えてください
今までの広報室ページ
広報日記
- 2月22日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2025年度 第2回 星のかけらを手にして-隕石と小惑星に隠された生命誕生のヒント
- 物理学専攻新博士修士 講演会・授賞式・祝賀会を執り行いました
- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました
- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました
- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました